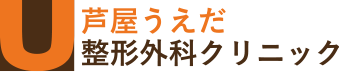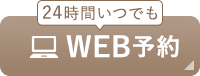- 交通事故に遭われた方へ
- 交通事故後によくある症状
- 交通事故後の治療は整骨院と整形外科、
どっちに行くべき? - 交通事故にあった時の対応から治療までの流れ
- 労災に遭われた方へ
- 労働災害の認定条件
- 労働災害申請までの流れ
- 労災申請時に必要な書類・情報
- よくある質問
交通事故に遭われた方へ
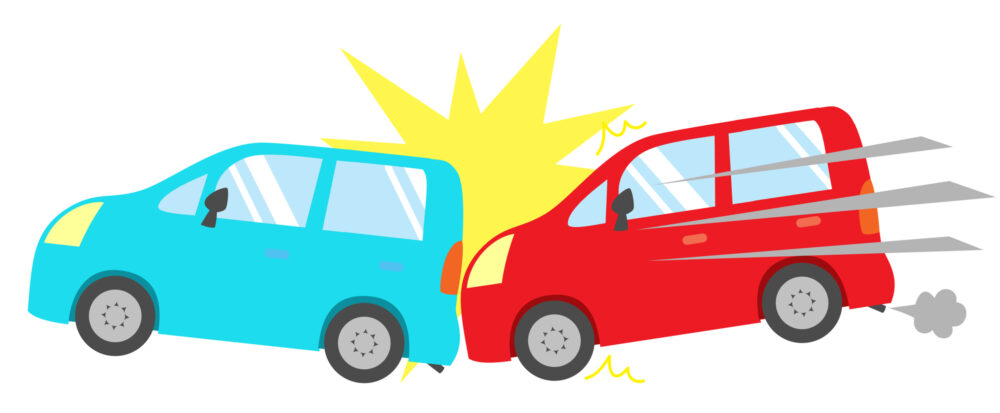 交通事故で怪我を負ったとしても、すぐに症状が現れるとは限りません。特にむちうちは、数時間後~数日後に初めて症状が現れることが少なくありません。事故直後は心が興奮状態にあり、痛みを感じにくいということも影響します。
交通事故で怪我を負ったとしても、すぐに症状が現れるとは限りません。特にむちうちは、数時間後~数日後に初めて症状が現れることが少なくありません。事故直後は心が興奮状態にあり、痛みを感じにくいということも影響します。
交通事故に遭われた場合には、痛みなどの症状の有無に関係なく、すぐに当院にご相談ください。早期治療により、予後が良くなる可能性が高くなります。
また、時間が経ってから医療機関を受診すると、その怪我と交通事故の因果関係が認められないということもあります。損害賠償請求にも関わってくることなので、そういった意味でも早期受診が大切になります。
交通事故後によくある症状
むちうち、打撲・骨折・脱臼などに伴う症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 首の痛み
- 首を回しにくい、動かすと痛い
- 肩や背中、腰の痛み
- 手足の痛み、しびれ
- 関節の可動域の減少
- その他の各部位の痛み、腫れ
- 倦怠感
- 頭痛
- 吐き気、めまい
- 耳鳴り
- 食欲不振 など
交通事故後の治療は整骨院と
整形外科、どっちに行くべき?
交通事故後の診断や治療を受けるためには、整形外科を受診しなければなりません。整骨院では医療行為ができず、患部への施術のみ可能です。レントゲン検査、MRI検査などもできません。
また、整形外科と整骨院の両方に通うということもできますが、整骨院に偏重して通った場合、後遺障害診断が受けられないということもあります。
なお当院では、上記のような理由から、整骨院との併用治療には対応しておりません。予めご了承ください。
交通事故にあった時の対応から治療までの流れ
1交通事故の直後
警察への届け出
交通事故に遭ったら、必ず警察に届け出をしましょう。
交通事故証明書が交付されます。
加害者の身元確認
相手方の氏名・住所・連絡先、および車のナンバー・加入している保険会社、証明書番号を確認しましょう。
また相手方が業務中であった場合には、会社名・住所・連絡先の確認も必要です。
目撃者の確認
互いの言い分に食い違いが出る等のトラブルに備え、目撃者の方がいれば、連絡先を教えてもらいましょう。
保険会社への連絡
加入されている保険会社に連絡を取りましょう。またこれから受診する医療機関の名称・住所などを伝えます。
このタイミングで保険会社に連絡を入れておき、受診までに保険会社と医療機関の連絡がつけば、患者様の窓口負担はありません。
※連絡が間に合わない場合は一旦窓口でご負担いただき、確認が取れ次第返金となります。
2整形外科等の医療機関の受診
窓口にて、交通事故に遭い、診断・治療を希望している旨をお伝えください。
問診票をお渡ししますので、ご記入をお願いします。難しい場合、スタッフが代理で記入をいたします。
3検査・診断・治療
症状、受傷の状況などについて医師が確認します。
その上で、視診・触診・レントゲン検査・超音波検査・MRI検査・血液検査など、必要な診察・検査を行い、診断します。
当院では、上記すべての検査を院内で行うことができます。
診断の結果に基づき、治療を開始します。
4保険会社への連絡
受診した旨を、加入されている保険会社へとご連絡ください。
その後は、保険会社の担当者から指示やアドバイスがございます。
労災に遭われた方へ
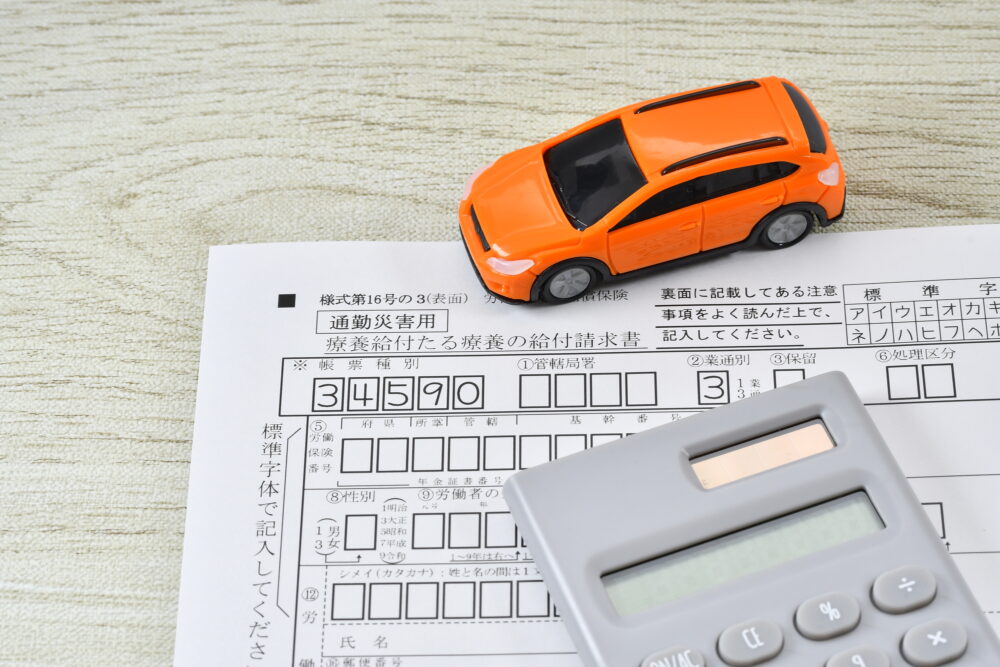 労災(労働災害)とは、仕事中、通勤途中などに負った怪我、および仕事を原因として発症した病気のことを指します。
労災(労働災害)とは、仕事中、通勤途中などに負った怪我、および仕事を原因として発症した病気のことを指します。
労災による怪我・病気の治療費は、労働者災害補償保険法に基づいて制定された「労災保険」によってまかなわれます。
当院は労災保険指定医療機関ですので、この労災保険を使った労災の治療を行うことができます。仕事中や通勤途中に怪我を負った方は、当院にご相談ください。
労働災害の認定条件
その会社の従業員であれば、正社員・契約社員・パート・アルバイトといった雇用形態に関係なく、労災保険の対象となります。
業務中の労災
業務中に社内や社外で起こったあらゆる怪我、業務によって発症した病気(感染症・過労による脳や心臓の病気・うつ病など)のことを指します。
本人の不注意性については基本的に問われません。
通勤中の労災
職場への行き・帰りの道中で起こった怪我を指します。
ただし、寄り道などで通常の通勤路から外れたルートで怪我を負った場合には、原則として労働災害とは認められません。
労働災害申請までの流れ
1会社への報告
労災が発生したら、すぐに会社(自社)へと報告をしてください
2整形外科等の医療機関の受診・治療
労災の種類(どのような怪我か・病気か)に応じて、各医療機関を受診し、治療を受けます。
受診の際には、労災の治療を目的として受診されたことを受付にお伝えください
3申請書類の作成
従業員からの報告、従業員が受診した医療機関からの請求書をもとに、会社は労災保険の給付に必要な申請書類を作成します。
申請書類は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。
4申請書類の提出
従業員の治療が落ち着いたタイミングで、会社は労災保険の給付に必要な申請書類を、労働基準監督署へと提出します。ご自身で提出することもあります。
5調査・給付
労働基準監督署が調査を行い、労災と認められると、従業員の方が給付金を受け取ることができます。通常、1~3ヶ月ほどの期間を要します。
労災と認められず、そのことに不服がある場合には、労働局へと審議を請求することができます。
労災申請時に必要な書類・情報
労災申請時には、以下の書類、情報が必要です。
書類
| 療養(補償)等給付たる療養の給付請求書 | |
| 業務上の災害により、初めて医療機関を受診する時 | 様式第5号 |
|---|---|
| 通勤中の災害により、初めて医療機関を受診する時 | 様式第16号の3 |
| 業務上の災害の治療を受ける医療機関を変更(転院)する時 | 様式第6号 |
| 通勤中の災害の治療を受ける医療機関を変更(転院)する時 | 様式第16号の4 |
| 休業等給付申請をする時 | 様式第8号、様式第16号の6 |
| 障害等給付申請をする時 | 様式第10号、様式第16号の7 |
いずれも、厚生労働省のHPからダウンロードが可能です。
情報
労働保険番号
労災保険に加入する企業に割り振られた番号です。
従業員からの依頼に備えて、企業側が確認しておく必要があります。
事業主証明
労災給付申請書に記載する内容です。負傷・発病の年月日、災害の原因や発生状況などのことを指します。
よくある質問
交通事故治療で
よくある質問
相手方が無保険である場合でも、治療は受けられますか?
はい、可能です。相手方が保険に入っていない、またはひき逃げをしたといった場合には、「政府保障事業」という保障制度を利用し治療を受けられます。
ただし、この制度には法廷限度額が定められています。超過分が患者様の全額負担とならないよう、健康保険を利用します。そのため、マイナ保険証または健康保険証をお持ちください。
また加入されている保険の種類によっては、相手方が無保険であった場合の補償が組み込まれています。
保険会社の治療費の支払いは、いつまで続きますか?
通常、これ以上の治療を継続しても、症状が良くなることが期待できない(症状固定)と医師が判断したタイミングで支払いが終了します。
交通事故によって負った怪我の後遺症が残った場合、どうなりますか?
症状固定となっても、後遺症が残っている場合には、後遺障害認定のため手続きを行います。医師が後遺障害診断書を作成し、その内容を受けて後遺症の等級認定が下りれば、症状固定以降の治療費・休業損害・入通院慰謝料を損害賠償請求することができます。
労災治療でよくある質問
労災治療を受ける場合、必要な書類を教えてください。
「療養(補償)等給付たる療養の給付請求書」を厚生労働省のHPからダウンロード・印刷してお持ちください。業務中の災害であれば「様式第5号」が、通勤中の災害であれば「様式第16号の3」が必要です。
ただ、急なことで用意できないということもあります。その場合には、後日お持ちいただければ構いません。
その他、労災保険が適用されなかった場合に備えて、マイナ保険証(健康保険証)もお持ちください。
「療養(補償)等給付たる療養の給付請求書」を持って行かなかった場合にも、治療費はかからないのでしょうか?
給付請求書がない場合、恐れ入りますが、一旦患者様にお支払いをお願いすることとなります。ただ、マイナ保険証(健康保険証)をお持ちであれば、その負担割合に応じたお支払いとなります。もちろん、後日に給付請求書をお持ちいただければ、お支払いになった全額をお返しできます。