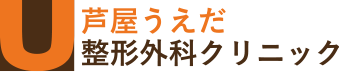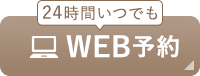背中が痛い
 背中の痛みは、筋肉や背骨の異常が原因となることが多く、整形外科の診療領域に含まれます。軽度の痛みであれば、安静にすることで自然に回復することもありますが、症状が長引く場合や悪化する場合は注意が必要です。
背中の痛みは、筋肉や背骨の異常が原因となることが多く、整形外科の診療領域に含まれます。軽度の痛みであれば、安静にすることで自然に回復することもありますが、症状が長引く場合や悪化する場合は注意が必要です。
特に、高齢者では骨粗鬆症による圧迫骨折が原因となることがあり、放置すると寝たきりのリスクが高まります。また、背骨の異常が進行すると、歩行困難につながるケースもあります。背中や腰の痛みは体からのSOSサインです。違和感を感じたら、早めに整形外科を受診し、適切な診断・治療を受けることが大切です。
背中の痛み以外にもこんな症状はありませんか?
背中の痛みは、筋肉や背骨、神経の異常が関係していることが多く、痛み以外にもさまざまな症状を引き起こすことがあります。
下記のような症状がある場合、放置せず、早めに整形外科を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

- 背中に違和感やしびれを感じることがある
- 特に起き上がる際や動作時に強く痛む
- 首の後ろから背中、胸にかけて痛みが広がることがある
- 背中がねじれている、腰の位置が左右非対称になっている
- 手にも痛みやしびれを感じる
背中が痛い原因と考えられる病気
脊椎圧迫骨折
主に高齢者や骨粗鬆症の方に多く見られる骨折で、背骨(脊椎)が押しつぶされるように変形することで発症します。転倒や重い物を持ち上げる動作などで起こることが多いですが、骨がもろくなっている場合は特に強い衝撃がなくても骨折することがあります。初期は軽い腰痛や背中の痛みとして現れますが、進行すると姿勢が前かがみになったり、身長が低くなったりすることがあります。
頚椎椎間板ヘルニア
首の骨(頚椎)の間にある椎間板が変性し、神経を圧迫することで発症します。首の痛みや肩こりに加えて、腕や手にしびれや痛みが生じることが特徴です。症状が進行すると、力が入りにくくなり、細かい作業が難しくなることもあります。長時間のデスクワークや加齢が主な原因となるため、生活習慣の見直しや適切な治療が大切です。
変形性脊椎症
加齢に伴い背骨(脊椎)が変形し、骨棘(こつきょく)と呼ばれる突起ができることで痛みやしびれを引き起こす疾患です。首や腰に起こりやすく、動作時の痛みやこわばりが特徴です。進行すると、脊柱管狭窄症を伴い、神経を圧迫することで手足のしびれや歩行障害が現れることもあります。適度な運動や姿勢の改善が有効です。
側弯症
背骨が左右に曲がる疾患で、成長期の子どもや思春期に発症することが多いです。原因不明の「特発性側弯症」が最も多く、軽度の場合は自覚症状がほとんどありません。しかし、進行すると肩の高さが違う、腰の位置が左右非対称になるなど、外見の変化が生じます。重度の場合は内臓を圧迫し、呼吸機能や内臓の働きに影響を及ぼすこともあります。
後縦靱帯骨化症
脊椎の後縦靱帯が骨に変わり、脊髄を圧迫する疾患です。首(頚椎)に多く見られ、初期症状として首や肩のこわばり、手足のしびれが現れます。進行すると、歩行障害や排尿・排便のコントロールが難しくなることもあります。原因は明確ではありませんが、遺伝的要因や糖尿病との関連も指摘されています。
黄色靱帯骨化症
脊椎の後方にある黄色靱帯が骨化し、脊髄を圧迫する疾患です。胸椎に発症することが多く、足のしびれや歩行障害が主な症状として現れます。進行すると、歩くとすぐに足が疲れる、つまずきやすくなる、排尿・排便障害が起こることもあります。原因は明らかではありませんが、日本人に多く、加齢や遺伝的要因が関係すると考えられています。
背中が痛い時に行う診断と検査
問診・診察
背中の痛む部位、痛み方などについて詳しくお伺いいたします。視診や触診を行い、筋肉や骨の状態も調べます。
レントゲン検査
骨の異常、脊柱の配列異常、椎間板の異常がないか、レントゲン検査を行います。
超音波検査
神経の圧迫、筋肉や靭帯の異常、血流の状態などを調べるため、超音波検査を行います。
MRI検査
神経や脊髄の異常、椎間板の異常、軟部組織の異常をMRI検査で確認します。
その他、CT検査、筋電図、神経伝導検査が必要な場合は連携病院等をご紹介します。
また、心疾患、消化器疾患などが疑われる場合にも、速やかに専門の医療機関へとご紹介しますのでご安心ください。
背中が痛い時の治療
薬物療法
 消炎鎮痛薬の内服、湿布の外用などを処方します。
消炎鎮痛薬の内服、湿布の外用などを処方します。
基本的に対症療法となりますので、お薬だけに頼っていると、使用を終えた後の再発リスクが高まります。セルフケアやリハビリテーションなどにも、しっかりと取り組んでいきましょう。
リハビリテーション
痛みが強い間は安静にしてください。
痛みが落ち着いてからは、温熱・電気・牽引などの物理療法、筋力トレーニング・ストレッチなどの運動療法を行います。
また、日常動作の指導などを行い、症状の改善と再発防止を図ります。
注射療法
薬物療法やリハビリテーションで十分な効果が得られない場合には、トリガーポイント注射、ブロック注射などを行います。
また当院では、癒着した筋膜・神経を剥がすハイドロリリースにも対応しております。
装具療法
必要に応じて、安静を保つための装具を使用します。
手術療法
保存療法で十分な効果が得られない場合には、疾患に応じた手術を検討します。
手術が必要な場合は、速やかに提携する医療機関をご紹介します。