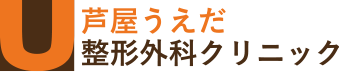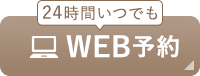野球肘/テニス肘/ゴルフ肘とは
野球肘、テニス肘、ゴルフ肘とは、野球・テニス・ゴルフを繰り返しプレーする動作の中で起こりやすい、肘のスポーツ障害です。
野球肘、テニス肘、ゴルフ肘はあくまで一般名であり、それぞれ正式には「上腕骨内側上顆炎」「上腕骨外側上顆炎」「上腕骨内側上顆炎」と言います。
また、必ずしも野球・テニス・ゴルフをする人だけに起こるものではありません。似た動作を伴う他のスポーツ、あるいは日常生活中の特定の動作の繰り返しでも、上腕骨内側上顆炎や上腕骨外側上顆炎を発症することがあります。
野球肘
(離断性骨軟骨炎・
内側側副靭帯損傷)
 野球における「投球動作の繰り返し」を主な原因とします。
野球における「投球動作の繰り返し」を主な原因とします。
ポジション別では、ピッチャーによく見られます。また、小学生~高校生の成長期にあたるお子様に好発します。
テニス肘
(上腕骨外側上顆炎)
 テニスにおける「ラケットを強く握る・ボールを打つ動作の繰り返し」を主な原因とします。
テニスにおける「ラケットを強く握る・ボールを打つ動作の繰り返し」を主な原因とします。
野球肘とは異なり、中高年の方によく見られます。
ゴルフ肘
(上腕骨内側上顆炎)
 ゴルフにおける「スイング動作の繰り返し」を主な原因とします。
ゴルフにおける「スイング動作の繰り返し」を主な原因とします。
手や腕をよく使う職業の方(デスクワークなどパソコンのタイピング、大工・建設作業員、調理師、美容師など)によく見られます。またそのような負担がなくても発症することもあります。
野球肘/テニス肘/ゴルフ肘の症状
野球肘、テニス肘、ゴルフ肘ではそれぞれ、痛む位置、痛みが強くなる動作が異なります。
野球肘の症状
野球肘では、肘の内側に痛みが出ます。
痛みは、肘の曲げ伸ばしの時、重い物を持ち上げる時に強くなります。
テニス肘の症状
テニス肘では、肘の外側に痛みが出ます。
痛みは、腕を伸ばして物を掴む時、物を持ち上げる時に強くなります。
ゴルフ肘の症状
ゴルフ肘では、肘の内側に痛みが出ます。
痛みは、手首を曲げたりひねったりする時、物を持ち上げたり重いものを持つ時、キーボードのタイピングやハサミ、包丁を使う時に強くなります。
野球肘/テニス肘/ゴルフ肘の原因
野球肘、テニス肘、ゴルフ肘でそれぞれ、具体的にどのような運動が原因になるのかを解説します。
野球肘の原因
野球の場合には「投球動作の繰り返し」が主な原因となります。
具体的には、手首を内側に曲げる運動の繰り返しです。
また日常生活中においては、肘を曲げた状態での作業、重い物を持つ動作なども、原因の1つとなります。
テニス肘の原因
テニスの場合には「ラケットを強く握る・ボールを打つ動作の繰り返し」が主な原因となります。
具体的には、手首を外側に曲げる(反らす)動作の繰り返しです。
日常生活においては、重い物を持つ動作(赤ちゃんの抱っこ等)も原因の1つになります。その他、出産などに伴う女性ホルモンのバランスの乱れが、上腕骨外側上顆炎の発症に影響するとも言われています。
ゴルフ肘の原因
ゴルフの場合には「スイング動作の繰り返し」が主な原因となります。
具体的には、手首を内側に曲げる(クラブを引く・振り下ろす・ボールを打つなど)動作の繰り返しです。
日常生活においては、タオルやぞうきんを絞る動作、重い物を持つ動作、物をつかんで持ち上げる動作、キーボードのタイピングなども原因となります。
野球肘/テニス肘/ゴルフ肘の
診断と検査
野球肘やテニス肘、ゴルフ肘が疑われる場合には、問診や診察の上、以下のようなテストを行い、診断します。
手関節屈伸テスト
(トムセンテスト)
肘を伸ばして手を前方に突き出し、手首を反らせた体勢をとっていただきます。
その状態で、医師が患者様に対して、手首を内側に曲げる力を加えます。その際に肘の痛みの有無・位置を確認します。
チェアテスト
肘を伸ばして手を前方に突き出し、その手で椅子を持ち上げ、肘の痛みの有無・位置を確認します。
中指伸展テスト
肘・手首・手指を伸ばした状態で手を前方に突き出していただきます。
その状態で、医師が患者様に対して、中指を内側に押します。その際に肘の痛みの有無・位置を確認します。
野球肘/テニス肘/ゴルフ肘の治療
安静に努める
野球・テニス・ゴルフは中断し、受診まで安静にしてください。安静にして痛みが引いた場合も、自己判断での再開は厳禁です。ランニング、筋力トレーニングなどの運動ができるかどうかは、医師に相談してください。
薬物療法
 消炎鎮痛薬の内服、湿布の外用などを処方します。
消炎鎮痛薬の内服、湿布の外用などを処方します。
基本的に対症療法となりますので、お薬だけに頼っていると、使用を終えた後の再発リスクが高まります。セルフケアやリハビリテーションなどにも、しっかりと取り組んでいきましょう。
リハビリテーション
痛みが強い間は安静にしてください。
痛みが落ち着いてからは、温熱・電気・超音波などの物理療法、筋力トレーニング・ストレッチなどの運動療法を行います。
また必要に応じて、フォームの指導なども行います。
注射療法
薬物療法やリハビリテーションで十分な効果が得られない場合には、関節注射、ヒアルロン酸注射などを行います。
PRP療法 (PFC-FD™療法)
 患者様ご自身の血液中の成長因子を抽出・活性化させた「PRP(多血小板血漿)」を用いた再生療法です。当院では、PRPを凍結乾燥(フリーズドライ)させたPFC-FDを患部へと注入するPFC-FD療法を行っています。豊富な成長因子が組織の修復を促し、痛みを軽減させます。
患者様ご自身の血液中の成長因子を抽出・活性化させた「PRP(多血小板血漿)」を用いた再生療法です。当院では、PRPを凍結乾燥(フリーズドライ)させたPFC-FDを患部へと注入するPFC-FD療法を行っています。豊富な成長因子が組織の修復を促し、痛みを軽減させます。
近年では、メジャーリーガーの大谷翔平選手が受けたことでも話題となり、アスリートの間でも注目を集めています。
薬物療法で十分な効果が得られない、手術を回避したい(高齢であり受けられない)といった方に、特におすすめします。
手術療法
上記の治療で十分な効果が得られなかった場合には、手術を検討します。
肘関節の状態に応じて、さまざまな術式が選択されます。
手術が必要な場合は、速やかに提携する医療機関をご紹介します。
野球肘/テニス肘/ゴルフ肘の
対処・予防方法
対処方法
肩甲骨のストレッチ
早い球を投げる、強いショットを打つといった場合には、手指・手首・肘だけでなく、肩から動かすことがとても大切になります。そしてこれらの関節を連続して動かすことで、負荷が分散されます。
日ごろから、肩甲骨の開きを良くするストレッチをしておくのがおすすめです。
筋肉のバランスを整える
上半身と下半身、身体の右側と左側を見て、筋肉の偏りがある場合には、トレーニングを工夫してバランスを整えます。バランスが悪いと、偏った部位に負荷がかかり、怪我のリスクも高くなります。
生活習慣の改善
栄養バランスの良い食事、十分な休養・睡眠は、疲労回復、怪我・スポーツ障害の予防につながります。
もちろん、パフォーマンス向上のためにも大切になります。
温冷交代浴
1分温め、30秒冷やすという入浴を2~3回繰り返すことで、疲労の回復に効果があると言われています。
※心臓の弱い方、中高年の方はお控えください。
予防方法
生活習慣の改善
予防においても、栄養バランスの良い食事、十分な休養・睡眠は欠かせません。
ストレッチ
肩甲骨のストレッチ、手首・肘のストレッチを習慣化することをおすすめします。
姿勢・フォームの改善
普段の姿勢やフォームを改善することで、野球肘やテニス肘のリスクを下げることができます。
サポーターの着用
肘や手首のサポーターの着用によって、野球肘・テニス肘のリスクを下げる効果が期待できます。