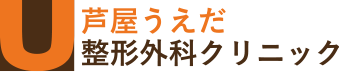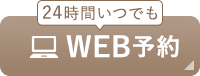- 肩関節周囲炎(五十肩・四十肩)とは
- 五十肩・四十肩の違い
- 肩関節周囲炎(五十肩・四十肩)の症状
- 悪化するとどうなる?肩関節周囲炎の
ステージ(経過) - 肩関節周囲炎(五十肩・四十肩)の原因
- 肩関節周囲炎(五十肩・四十肩)の診断と検査
- 肩関節周囲炎(五十肩・四十肩)の治療
- 肩関節周囲炎(五十肩・四十肩)の人が
やっていけないこと
肩関節周囲炎
(五十肩・四十肩)とは
 肩関節のまわりにある関節包・腱板の炎症などにより、腕を上げる動作で肩が痛む状態を指します。悪化すると、安静時にも痛む、痛みで腕が上げられないなど、日常生活に大きな支障をきたします。着替え、洗髪などの動作が辛いというお声がよく聞かれます。
肩関節のまわりにある関節包・腱板の炎症などにより、腕を上げる動作で肩が痛む状態を指します。悪化すると、安静時にも痛む、痛みで腕が上げられないなど、日常生活に大きな支障をきたします。着替え、洗髪などの動作が辛いというお声がよく聞かれます。
痛みで肩を動かさないようになると、可動域が減少し、治療・リハビリに要する時間も長くなります。「腕を上げると肩が痛い」と感じたら、放置せずにお早目に当院までご相談ください。
五十肩・四十肩の違い
40代で発症した肩関節周囲炎を四十肩、50代で発症した肩関節周囲炎を五十肩と呼ぶだけで、肩関節周囲炎であること、症状の強さなどは関係ありません。
好発年齢は40~50代ですが、30代や60代など、他の年代で発症することもあります。
肩関節周囲炎
(五十肩・四十肩)の症状
痛み

- 腕を上げた時や動かした時の肩の痛み
- 安静時の肩の痛み
- 睡眠中の肩の痛み(痛みで寝付けない、目が覚める)
運動制限
- 最初は、痛みによって腕や肩の動かしづらさを感じる
- その後、拘縮によって肩の可動範囲が狭まると、腕を上げようにも上げることが難しくなる
悪化するとどうなる?
肩関節周囲炎の
ステージ(経過)
放置して悪化した場合
肩関節周囲炎が悪化すると、痛みがひどくなり、安静時や睡眠中に痛む、痛みで腕を上げられない等の症状が現れます。また、肩や腕の運動制限が生じます。これらの症状によって、日常生活に大きな支障をきたすようになります。
肩関節周囲炎のステージ(経過)
肩関節周囲炎の経過は、炎症期・拘縮期・回復期という3つのステージに分けられます。
炎症期
炎症によって、痛みが出始める時期です。
通常はまず、腕を上げる動作で痛みに気づきます。その後、安静時にも痛む、痛くて腕を上げられない等の症状が現れます。
拘縮期
炎症・痛みは落ち着きますが、痛みによって肩を動かさなかった期間があったことで、肩関節が拘縮します。
可動域を超えて腕を動かそうとした場合には、肩関節に強い痛みが出ます。安静時の痛みは少ないものの、だるい感じ・重い感じが認められます。
回復期
治療を行うことで、次第に肩を動かしても痛みが出にくくなります。ただ、可動域は一気に回復しません。無理に動かすと、炎症・痛みが再発することもあるため、医師や理学療法士の指示を守りながら、治療を継続しましょう。
肩関節周囲炎
(五十肩・四十肩)の原因
肩関節周囲炎の主な原因は、加齢です。また、肩関節への過度の負荷が原因になることもあります。
加齢・負荷によって肩関節の周囲組織が損傷し、炎症を起こすことで、肩関節周囲炎を発症します。
その他、ホルモンバランスの乱れ、血行不良なども、肩関節周囲炎の発症に影響することがあると言われています。
肩関節周囲炎
(五十肩・四十肩)の
診断と検査
問診・診察
肩の痛みについて、詳しくお伺いします。
また、視診・触診により、肩関節の状態や動きを確認します。
レントゲン検査
肩関節周囲炎では骨に異常はありませんが、骨折等の外傷を除外するため、レントゲン検査を行います。
超音波検査
軟部組織の状態を観察したり、肩関節の炎症の有無や程度を調べるため、超音波検査を行います。
MRI検査
肩関節周囲炎以外の疾患の除外、軟部組織の観察、炎症の経過の評価などを目的として、MRI検査を行うことがあります。
その他CT検査、筋電図、神経伝導検査が必要な場合は連携病院等をご紹介します。
肩関節周囲炎
(五十肩・四十肩)の治療
薬物療法
 非ステロイド性抗炎症薬の内服、湿布の外用などを処方します。
非ステロイド性抗炎症薬の内服、湿布の外用などを処方します。
基本的に対症療法となりますので、お薬だけに頼っていると、使用を終えた後の再発リスクが高まります。セルフケアやリハビリテーションなどにも、しっかりと取り組んでいきましょう。
リハビリテーション
痛みが強い間は安静にしてください。
痛みが落ち着いてからは、炎症・痛みの改善、拘縮の改善のため、温熱・電気・超音波・牽引などの物理療法、筋力トレーニング・ストレッチなどの運動療法を行います。
注射療法
薬物療法やリハビリテーションで十分な効果が得られない場合には、関節注射、トリガーポイント注射、ハイドロリリースなどを行います。
各時期別の治療方法
炎症期
炎症・痛みの改善が最優先となります。
薬物療法を行いながら、ご自宅では安静にしてください。痛みが強い場合には、三角巾を使用することもあります。
拘縮期
炎症・痛みは落ち着いていますので、少しずつ運動を行い、拘縮の進行を防ぎます。
痛みがある場合には、薬物療法も併用します。
回復期
拘縮が残らないよう、しっかりとストレッチ、筋力強化のための運動を行います。
回復期にリハビリをしても拘縮・可動域が改善せず、日常生活に支障をきたす場合には、手術を検討します。
肩関節周囲炎
(五十肩・四十肩)の人が
やっていけないこと
痛みを我慢しながら仕事・
スポーツをする
痛みがあるということは、炎症があるということです。無理な運動をすると、炎症が悪化します。
人に手伝ってもらい、
腕を無理に上げる
痛みがあるのに、または可動域の限界を超えて、家族などに腕を上げてもらうといったことは、絶対におやめください。炎症や痛みが悪化する原因になります。
痛みが落ち着いてからも
動かさない
炎症期を過ぎ、痛みが落ち着いてからは、安静にし過ぎると拘縮が進行します。
拘縮期からは徐々に、回復期にはしっかりと、ストレッチや筋力トレーニングを行っていきましょう。