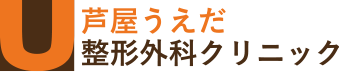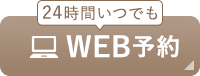- 変形性膝関節症とは
- 変形性膝関節症の症状
- どんな人がなりやすい?
- 変形性膝関節症の原因
- 変形性膝関節症の診断と検査
- 変形性膝関節症の治療
- 変形性膝関節症の人がしてはいけないこと
- 変形性膝関節症の予防法
- 膝の痛み・こわばりでお悩みの方は
ご相談ください
変形性膝関節症とは
 変形性膝関節症とは、中高年の方、特に女性に多い膝の病気です。軟骨が擦り減ることで、骨と骨がぶつかったり、骨棘が形成されることで痛みが出ます。
変形性膝関節症とは、中高年の方、特に女性に多い膝の病気です。軟骨が擦り減ることで、骨と骨がぶつかったり、骨棘が形成されることで痛みが出ます。
一度擦り減った軟骨が自然に再生することはなく、さらに進行すると膝関節の変形が起こります。
変形性膝関節症は、一次性変形性膝関節症と二次性変形性膝関節症に分けられます。全体のうちほとんどを占める一次性変形性膝関節症は主に加齢を、二次性変形性膝関節症は外傷・先天異常・代謝異常を原因として発症します。
変形性膝関節症の症状
変形性膝関節症の主な症状は、「膝の痛み」と「膝の変形」です。
初期・中期・末期と、以下のように進行していきます。
初期
主に、動いた時に膝に痛みが出ます。
- 起き上がる時の痛み
- 動き出す時の痛み
- 歩行、階段の上り下り、方向転換の時の痛み
- 正座が辛い
中期
次第に、動かさなくても痛むようになります。また徐々に、膝の変形が現れます。
- 常に膝が痛む
- 痛みで正座をする、深くしゃがむ、階段を上り下りすることが難しい
- 痛みに加え、膝に腫れ、熱感が現れる
- 膝を曲げ伸ばしした時のきしむような音
- 膝に水が溜まる
- 膝の変形(O脚)
末期
末期になると、日常生活への支障はさらに大きくなります。
- 痛み、腫れん、熱感、曲げ伸ばしの困難などが、さらに悪化
- 歩く、立つ・しゃがむといった基本的な動作が難しい・できない
- 症状によって外出の機会が減る、意欲が低下する
どんな人がなりやすい?
変形性膝関節症のほとんどを占める一時性変形性膝関節症は、主に加齢を原因とします。そのため、中高年での発症がほとんどを占めます。
二次性変形性膝関節症は、主に外傷・先天異常・代謝異常を原因として発症するため、スポーツ・肉体労働をする比較的若い世代でも発症します。
また変形性膝関節症は、男性よりも女性に多く見られます。男性と比べて関節が小さい・筋肉が少ない・ハイヒールなど膝に負担をかける靴を履く人が多い・閉経を境に女性ホルモンが急激に減少することなどが影響しているものと思われます。
このようなことを考慮すると、以下のような人は、そうでない人よりも変形性膝関節症になりやすいと言えるでしょう。

- 中高年(特に50歳以上)
- 女性
- 太っている人
- 膝を酷使するスポーツ(サッカー、スキー、スノボなど)をしている人
- 膝を酷使する仕事(農業、漁業、重い物を運ぶ仕事など)をしている人
- 関節リウマチ、骨壊死の既往がある人
変形性膝関節症の原因
変形性膝関節症は、軟骨の擦り減りによって発症します。
ほとんどの変形性膝関節症は、加齢を原因として発症し、これを一時性変形性膝関節症と言います。
一方の二次性変形性膝関節症は、外傷・先天異常・代謝異常などを原因として、二次的に発症します。
その他、肥満、膝を酷使するスポーツ・仕事なども、変形性膝関節症のリスクを高めます。
変形性膝関節症の診断と検査
問診・診察
問診・視診・触診にて、症状の現れ方、膝の動き方、変形の程度などを確認します。
レントゲン検査
軟骨のすり減り、骨棘、骨の変形、骨硬化や骨嚢胞がないか、レントゲン検査を行います。
超音波検査
関節液の貯留、滑膜炎の有無、軟骨の厚みや損傷の状態を調べるため、超音波検査を行います。
MRI検査
軟骨のすり減りや損傷の詳細、半月板の変性や断裂の有無、靭帯・筋肉・滑膜の炎症や損傷、骨の内部にダメージはないか、MRI検査で確認します。
血液検査
炎症の有無や、関節リウマチとの鑑別、痛風との鑑別、骨粗鬆症の疑いはないか確認します。
その他CT検査、筋電図、神経伝導検査が必要な場合は連携病院等をご紹介します。
変形性膝関節症の治療
薬物療法
消炎鎮痛薬や抗炎症薬(NSAIDs)の内服などを処方します。
基本的に対症療法となりますので、お薬だけに頼っていると、使用を終えた後の再発リスクが高まります。セルフケアやリハビリテーションなどにも、しっかりと取り組んでいきましょう。
リハビリテーション
痛みが強い間は安静にしてください。
痛みが落ち着いてからは、温熱・電気・超音波などの物理療法、膝関節まわりの筋力・柔軟性を高めるための筋力トレーニング・ストレッチなどの運動療法を行います。
特に、大腿四頭筋を鍛えると、膝への負担、痛みの軽減が期待できます。
注射療法
薬物療法やリハビリテーションで十分な効果が得られない場合には、ヒアルロン酸注射、ステロイド注射などを行います。
装具療法
膝サポーター、インソールの使用の使用によって、膝への負担を軽減します。
ただし、膝サポーターの長期使用は筋力低下を招くおそれがあるため、期間を限定して使用します。
体外衝撃波治療
当院では、拡散型体外衝撃波治療を導入し、保険診療内のリハビリテーションの一環として提供しています。この治療法は、65ヵ国以上で使用されており、メジャーリーガーの大谷翔平選手を含む多くのアスリートが利用しています。筋肉や腱の炎症による慢性的な痛みに対して高い効果が期待できるため、スポーツ選手だけでなく、長引く痛みに悩む方にも適した治療法です。
Coolief(クーリーフ)
Coolief(クーリーフ)とは、変形性膝関節症が適応となる高周波を使った治療(保険診療)です。
痛みを感じる感覚神経を部分的に焼灼し、痛みを軽減します。
保存療法を行っても痛みが改善しない方、手術を受けられない方におすすめします。また、人工関節置換術後に残った痛みの緩和を目的として使用することもできます。
PRP療法(PFC-FD™療法)
患者様ご自身の血液中の成長因子を抽出・活性化させた「PRP(多血小板血漿)」を用いた再生療法です。当院では、PRPを凍結乾燥(フリーズドライ)させたPFC-FDを患部へと注入するPFC-FD療法を行っています。豊富な成長因子が組織の修復を促し、痛みを軽減させます。
近年では、メジャーリーガーの大谷翔平選手が受けたことでも話題となり、アスリートの間でも注目を集めています。
薬物療法で十分な効果が得られない、手術を回避したい(高齢であり受けられない)といった方に、特におすすめします。
手術療法
保存療法・再生医療(APS療法)で十分な効果が得られない場合には、手術を検討します。
人工関節置換術、骨切り術などの方法があります。
手術が必要な場合は、速やかに提携する医療機関をご紹介します。
変形性膝関節症の人が
してはいけないこと
痛みを我慢して膝を動かす
痛みがあるにもかかわらず、その痛みを我慢して膝を動かすといったことは控えましょう。
特に、可動域が狭くなっているのに限界以上まで動かす、人に手伝ってもらって無理に動かすといったことはしないでください。
受診まで、安静にして過ごしましょう。
膝を酷使する運動
たとえ治療によって痛みが軽減したとしても、膝を酷使する運動は控えましょう。膝に負荷をかければかけるほど軟骨は擦り減ります。そして一度擦り減った軟骨が、自然に再生するということはありません。
運動については、医師・理学療法士と相談して、その内容・強度を決めるようにしてください。
変形性膝関節症の予防法
肥満の解消
変形性膝関節症の主な原因は、加齢です。ただ、加齢を止めることはできません。
肥満気味の方は体重を減らすことで、膝への負担を軽減することができます。
膝まわりの筋力強化
膝まわりの筋力を強化することで、膝関節への負担を軽減することができます。
特に大腿四頭筋の強化がおすすめです。
膝に負担をかけにくい
環境を整える
お手洗いは和式ではなく洋式にする、布団ではなくベッドを使う、床に座るのではなく座椅子を使う等、膝に負担をかけにくい環境を整えましょう。
しゃがむ・正座をする・重い物を持って歩く(布団の上げ下ろし)といった動作や姿勢は、膝への負担が大きくなります。
禁煙・禁酒
喫煙・飲酒は、どちらも過度になると変形性膝関節症のリスクを高めると言われています。他の病気・怪我を予防するためにも、できる限り禁煙・禁酒をしましょう。
膝の痛み・こわばりで
お悩みの方はご相談ください
 膝の痛みやこわばりは、歩く・立つ・座るといった日常生活において欠かせない動作を不自由にします。外出をする機会が少なくなる、好きだったスポーツを諦めるきっかけになるということも少なくありません。
膝の痛みやこわばりは、歩く・立つ・座るといった日常生活において欠かせない動作を不自由にします。外出をする機会が少なくなる、好きだったスポーツを諦めるきっかけになるということも少なくありません。
背景に病気が隠れており、早急な治療が必要になるケースもあります。「歳のせいだから」と片付けず、症状が気になった時にはお早目に、お気軽に当院にご相談ください。