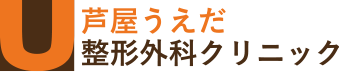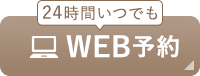手足がしびれる
 手足のしびれの多くは、手足の感覚を脳へと伝える神経に生じた何らかの異常・障害によって引き起こされます。
手足のしびれの多くは、手足の感覚を脳へと伝える神経に生じた何らかの異常・障害によって引き起こされます。
正座後のしびれは病気ではありませんが、実はこれも神経の一時的な障害(圧迫)を原因とする現象です。ご存じの通り、時間がたてば自然に治ります。
一方で、脊椎疾患、内科的疾患などの原因となって起こる手足のしびれもあります。「思い当たる原因のない手足のしびれ」「外傷後に生じた手足のしびれ」「感じたことのないタイプの手足のしびれ」に気づいた時には、お早目に当院にご相談ください。
ピリピリする?
手足のしびれの種類
しびれといっても、その種類は多様です。よく見られるしびれについて、ご紹介します。

- ピリピリ、チクチクと少し痛い感じがある
- ジンジン、ビリビリと電気が走っているような違和感がある
- 物を触った時の感覚が鈍い、物の温度を感じにくい
- 手足が重い、動きづらい、力が入りにくい感じがある
- 裸足なのに、足裏に紙がくっついているような感じがある
明らかな違和感はないけれど、物を落としてしまう・まっすぐ歩けない等の症状が見られることもあります。
手足のしびれの原因と
考えられる病気
脊椎疾患に原因がある
しびれ
椎間板ヘルニアや脊髄損傷、頸椎症、後縦靭帯骨化症、脊髄腫瘍など、脊椎疾患によるしびれです。
手足に伸びる末梢神経は脊髄・神経根とつながっていますので、脊髄・神経根が障害を受けると、手や足にしびれ・痛みが現れます。
脳神経疾患に原因がある
しびれ
脳卒中、脳腫瘍などにより神経細胞が損傷する・神経が圧迫されることで、手足にしびれが出ることがあります。
内科的疾患に原因がある
しびれ
糖尿病の三大合併症のうちの1つ、糖尿病神経障害では、手や足の神経が障害され、しびれや痛みが出ます。
その他、極端な偏食やアルコール依存症によるビタミン欠乏によって神経障害が起こり、手足のしびれを感じることもあります。
末梢神経に原因がある
しびれ
手根管症候群、足根管症候群、胸郭出口症候群、多発性ニューロパチー(末梢神経障害)などによるしびれです。
手足の神経の異常・障害によって、その手足に直接しびれ・痛みが出ます。
ストレスに原因がある
しびれ
ストレスによって自律神経のバランスが崩れ、しびれ、倦怠感、頭痛、動悸、イライラなどの症状が引き起こされることがあります。
不規則な生活リズム、睡眠不足も、自律神経のバランスを崩す原因になります。
若い女性がなりやすい?
更年期と関係はある?
 若い女性に「手足のしびれ」が見られる場合には、頚椎症、腰椎症などの可能性を十分に考えて診療する必要があります。妊娠中・産後などに見られる女性ホルモンの乱れが、頚椎症や腰椎症の発症に影響することがあると言われています。また、デスクワークをする若い女性も頚椎症・腰椎症には注意が必要です。
若い女性に「手足のしびれ」が見られる場合には、頚椎症、腰椎症などの可能性を十分に考えて診療する必要があります。妊娠中・産後などに見られる女性ホルモンの乱れが、頚椎症や腰椎症の発症に影響することがあると言われています。また、デスクワークをする若い女性も頚椎症・腰椎症には注意が必要です。
45~55歳くらいの女性の手足のしびれの場合には、更年期障害が原因になっていることがあります。必ず更年期障害になる、必ずしびれが出るというわけではありませんが、その可能性を考えて診療をいたします。
手足のしびれの診断と検査
問診・診察
症状の現れた時期、程度・頻度、しびれ以外の症状、既往歴などについて詳しくお伺いします。また視診、触診によって感覚や動きを確認します。
レントゲン検査
骨折や椎間板の変形、関節の異常、頚椎や腰椎の異常、脊柱の配列異常がないか、レントゲン検査を行います。
超音波検査
神経の圧迫、筋肉や靭帯の異常、血流の状態などを調べるため、超音波検査を行います。
MRI検査
脊髄や神経根の圧迫、神経の損傷や炎症、軟部組織や靭帯の異常をMRI検査で確認します。
血液検査
糖尿病、ビタミン欠乏症、甲状腺機能異常、炎症や感染症の疑いはないか確認します。
その他CT検査、筋電図、神経伝導検査が必要な場合は連携病院等をご紹介します。
手足のしびれがある時に
行う治療
薬物療法
 炎症・痛みがある場合、非ステロイド性抗炎症薬や抗炎症薬を処方します。
炎症・痛みがある場合、非ステロイド性抗炎症薬や抗炎症薬を処方します。
また必要に応じて、神経痛を直接和らげる薬も使用します。
基本的に対症療法となりますので、お薬だけに頼っていると、使用を終えた後の再発リスクが高まります。セルフケアやリハビリテーションなどにも、しっかりと取り組んでいきましょう。
リハビリテーション
痛みが強い間は安静にしてください。
痛みが落ち着いてからは、温熱・電気などの物理療法、筋力や柔軟性の維持・向上を図る筋力トレーニング・ストレッチなどの運動療法を行います。
手術療法
ヘルニアや骨棘などによって神経が圧迫されており、保存療法で十分な効果が得られない場合には、その圧迫を取り除く手術を検討します。
手術が必要な場合は、速やかに提携する医療機関をご紹介します。
生活習慣の見直し
姿勢の改善、減量、適度な運動、バランスの良い食事、十分な睡眠、ストレスの解消など、生活習慣を改善するためのアドバイスを行います。