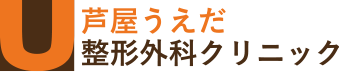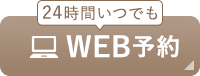- 肩が痛い
- 肩の痛みに伴う症状
- 何かの病気のサイン?肩の痛みの原因と
考えられる疾患 - こんな時は早めの受診を!病院に行くべきタイミング
- 肩が痛い時の診断と検査
- 肩が痛い時に行う治療
- 日常生活でできる予防とセルフケア
肩が痛い
 肩の痛みは、整形外科でとてもよく見られる症状です。
肩の痛みは、整形外科でとてもよく見られる症状です。
ただ、原因は実にさまざまで、適切な治療を行わないとなかなか良くなりません。診察の際には、どのような痛みがいつから発生し、どういった動作で強くなるかといったことを詳しくお聞かせください。必要に応じて画像検査などを行い、正確な診断、適切な治療を行います。
長く肩の痛みにお悩みの方も、ここ数日で痛くなってきたという方も、お気軽にご相談ください。
肩の痛みに伴う症状
肩の痛みと併発しやすい症状としては、以下のようなものがあります。
可動範囲の広い肩に痛みが出ることで、日常生活への支障も大きくなります。

- 腕を上げると肩が痛い
- ズキズキする
- 片方の肩だけが痛い、両肩が痛い
- 腕を動かした時に、肩に痛みが出る
- 眠れないほど強い肩の痛み
- 冷やしたり温めたりしても全然良くならない
- 着替え、洗髪などに支障が出ている
- 日常生活には問題ないが、スポーツの時に困る
- 運動をした後に肩が痛む
何かの病気のサイン?
肩の痛みの原因と
考えられる疾患
肩関節周囲炎
(四十肩・五十肩)
主に加齢を原因として肩関節のまわりの関節包・腱板で炎症が起こり、腕を上げた時に肩が痛みます。悪化すると、腕を上げなくても痛む、痛くて腕を上げられないといったように問題が大きくなります。また多くの場合、片方の肩だけでこの症状が起こります。
40代、50代で好発するため、四十肩・五十肩とも呼ばれます。
頚肩腕症候群(肩こり)
肩こりは、肩・首の筋肉の酷使や緊張、不良姿勢、運動不足、ストレスなどを原因として発生します。
肩から首にかけて、痛み、重さ、張りなどの不快感があります。血流の低下によって、頭痛や吐き気、めまいといった症状を伴うこともあります。
肩腱板断裂
肩関節の酷使や加齢によって、肩関節周辺の腱板が断裂した状態を指します。腕を上げた時や手を後ろに回した時、手を伸ばして物を取るといった時に痛みが出ます。安静時にも痛む、睡眠を妨げるほど強く痛むといったケースもあります。
石灰沈着性腱板炎
(肩石灰性腱炎)
肩関節周囲の腱板に石灰の一種(リン酸カルシウム)の結晶が沈着し、肩の痛みを引き起こします。夜間などに突然発症し、痛みによって腕を上げることが難しくなります。
石灰が沈着する原因について、はっきりしたことは分かっていませんが、40~50代の女性に好発します。
肩峰下インピンジメント
症候群
加齢や不良姿勢、スポーツ・仕事での肩の酷使を主な原因とする病気です。肩を上げる動作で腱板・滑液包が肩関節の骨にあたり、痛みが生じます。肩を下げた時に痛みが出る、安静時にも痛みがあるというケースも見られます。
こんな時は早めの受診を!
病院に行くべきタイミング
 以下のような場合には、特にお早目の受診をおすすめします。
以下のような場合には、特にお早目の受診をおすすめします。
- 安静時にも強く痛む、睡眠中に痛みで目が覚める
- 腕を上げるとひどく痛み、日常生活に支障をきたしている
- 突然、急激に肩の痛みが出てきた
- 肩を強くぶつけた直後から、痛みが出てきた
- 肩の痛みに加え、腫れ、熱感がある
- 肩をある方向へとまったく動かせない
もちろん、軽い痛み、日常生活には支障がないけれどスポーツの時に困るといった場合でも、受診していただけます。
肩が痛い時の診断と検査
問診・診察
肩の痛みについて、詳しくお伺いします。
また、視診・触診により、首周りの状態や動きを確認します。
レントゲン検査
骨折や脱臼、骨の変形、関節の変形、石灰沈着がないか、レントゲン検査を行います。
超音波検査
腱板や靭帯損傷、炎症の有無、関節内の水の溜まりの有無を調べるため、超音波検査を行います。
MRI検査
腱板断裂の有無、軟部組織や神経の異常、関節内部の詳細をMRI検査で確認します。
その他CT検査、筋電図、神経伝導検査が必要な場合は連携病院等をご紹介します。
肩が痛い時に行う治療
問診・診察、画像検査などをもとに診断し、以下のような治療を行います。
当院では、レントゲン検査に加え、MRI検査・超音波検査にも対応しております。
薬物療法
 痛み・炎症を抑えるための消炎鎮痛薬などを処方します。
痛み・炎症を抑えるための消炎鎮痛薬などを処方します。
基本的に対症療法となりますので、お薬だけに頼っていると、使用を終えた後の再発リスクが高まります。セルフケアやリハビリテーションなどにも、しっかりと取り組んでいきましょう。
リハビリテーション
痛みが強い間は安静にしてください。
痛みが落ち着いてからは、温熱・電気などの物理療法、筋力トレーニング・ストレッチなどの運動療法を行います。
再発防止のためには、肩回りの筋力アップも有効です。
注射療法
 薬物療法やリハビリテーションで十分な効果が得られない場合には、関節注射、トリガーポイント注射、ハイドロリリースなどを行います。
薬物療法やリハビリテーションで十分な効果が得られない場合には、関節注射、トリガーポイント注射、ハイドロリリースなどを行います。
手術療法
上記のような保存療法で十分な効果が得られない・見込めない場合には、手術を検討します。
手術が必要な場合は、速やかに提携する医療機関をご紹介します。
日常生活でできる予防と
セルフケア
 急性期には、保冷剤をタオルで包んだもの、氷嚢などで冷やすと、炎症・痛みの軽減が期待できます。
急性期には、保冷剤をタオルで包んだもの、氷嚢などで冷やすと、炎症・痛みの軽減が期待できます。
慢性化している場合には、入浴・ホットタオル・温湿布などで肩を温めると、痛みが軽減することが期待できます。痛みのない範囲でストレッチを行うのも有効です。
肩の痛みで眠れないという場合には、市販の痛み止めを飲んでくださっても構いません。ただこれはあくまで対症療法です。痛み止めを飲み続けるということはせず、その後できるだけ早く受診するようにしてください。
予防という意味では、姿勢に気をつけること、適度な運動をすること、規則正しい生活を送ることなどが大切になります。肩回りの筋力強化・ストレッチも有効です。