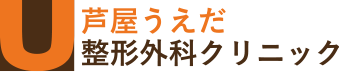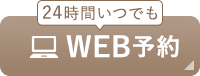- 首がこる、首こりは不調のもと?
- 頭痛やめまいも首こりのせい?
首のこりを伴う症状 - 首がこる主な5つの原因
- 自律神経と首こりの関係
- 首こりから考えられる病気
- 病院に行くべきタイミング
- 首のこりの診断と検査
- 首のこりに行う治療
- 日常生活でできる予防とセルフケア
首がこる、首こりは
不調のもと?
 こりといえば、肩こりを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。実際、肩こりに悩んで来院される方も少なくありません。ただ、診察をしてみると実は首がこっていた、首・肩の両方がこっていたということは少なくありません。「どんなこりですか?」とお聞きすると、「硬い」「張っている」「痛い」「重い」と、さまざまな感じ方があるようです。
こりといえば、肩こりを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。実際、肩こりに悩んで来院される方も少なくありません。ただ、診察をしてみると実は首がこっていた、首・肩の両方がこっていたということは少なくありません。「どんなこりですか?」とお聞きすると、「硬い」「張っている」「痛い」「重い」と、さまざまな感じ方があるようです。
首のこりでお悩みの患者様の中には、頭痛・めまい・吐き気などの他の症状を併発している方もいらっしゃいます。これらの症状が重なっている状態はとても辛いものです。
頚椎症、頚椎椎間板ヘルニアなどの疾患が背景に隠れていることもありますので、首のこりでお悩みの方は、お気軽に当院にご相談ください。
頭痛やめまいも首こりのせい?
首のこりを伴う症状
首のこりと併発しやすい症状には、以下のようなものがあります。

- 首~肩にかけてが硬い、張っている、痛い、重い
- 頭痛
- めまい
- 吐き気
- 手足のしびれ
- 筋力低下
- 感覚低下
頭痛、めまい、吐き気は、特に肩のこりを原因としているケースが多くなります。首のこりの治療を行うことで、これらの症状の改善が期待できます。
手足のしびれ、筋力低下、感覚低下がある場合には、何らかの疾患が原因になっている可能性が高まります。
首がこる主な5つの原因
頭を強く打ち付けたことによるダメージ
交通事故、スポーツ中の衝突などで起こりやすい、いわゆる「むちうち」です。頸椎に損傷が生じたために、そのまわりにある筋肉が硬くなってしまいます。
姿勢の悪さ
デスクワーク・運転・単調作業などによる長時間の同じ姿勢、あるいは普段からの不良姿勢などによって起こる首のこりです。首の筋肉が緊張することで、こりが生じます。
ホルモンバランスの変化
加齢、更年期・閉経などによるホルモンバランスの変化が、筋肉を緊張させてしまうということがあります。それまでまったく不調のなかった方が、40~50代で首などのこりを訴えるケースがよく見られます。
頚椎の変形
加齢によって、私たちの身体は少しずつ変化します。首の骨も例外ではなく、その変形によって筋肉に炎症が起こることで、こりの原因となることがあります。
ストレス
気分がふさいでいる時には、姿勢が悪くなったり、運動不足になったりしがちです。
また落ち込みがひどい時、うつ病を発症している時など、脳の活動の変化によって、首・背中のこりや痛みを感じやすくなることが分かっています。
自律神経と首こりの関係
生活リズムの乱れ、睡眠不足、ストレスなどは、自律神経のバランスを乱します。そして自律神経のバランスが乱れると、血流の低下、さらには筋肉のこりにつながります。自律神経のバランスを乱すような生活習慣をしている自覚がある方は、その改善に取り組むことで、首などのこりの軽減が期待できます。
生活習慣・自律神経の
バランスを整える
きっかけづくり
 生活リズムを正す・睡眠不足やストレスを解消する方法としておすすめしたいのが、運動です。現代日本では、デスクワークをする人の割合が増えています。昔のデスクワークと違い、デスクから離れる機会も少ないため、運動不足になりがちです。さらにテレワークをする人の場合は、通勤さえ不要です。
生活リズムを正す・睡眠不足やストレスを解消する方法としておすすめしたいのが、運動です。現代日本では、デスクワークをする人の割合が増えています。昔のデスクワークと違い、デスクから離れる機会も少ないため、運動不足になりがちです。さらにテレワークをする人の場合は、通勤さえ不要です。
運動によって適度な疲労感を得ることは、睡眠の質の改善・ストレスの解消に役立ちます。そして睡眠が改善すれば、生活リズムも整いやすくなります。また運動は、血流の改善などによる直接的なこりの解消効果も期待できます。
「生活習慣を改善する」と考えるとなかなか難しいものですが、生活習慣を改善する・自律神経のバランスを整えるきっかけとして、ぜひ運動をおすすめします。
※首に鋭い痛みがある・手足にしびれがある・運動をすると痛みが増すといった場合には無理をせず、お早目に当院にご相談ください。
首こりから考えられる病気
頚椎症
主に加齢を原因として頚椎(頚の骨)の構造が変性し、神経が圧迫されることで首・肩のこりや痛み、腕・手足の痛みやしびれ、脱力感などの症状が引き起こされます。またこれらの症状は、左右対称に現れます。
頚椎椎間板ヘルニア
加齢・外傷・運動などを原因として、頚椎の椎間板が変性し、脊髄・神経根を圧迫する病気です。神経の圧迫により、首の痛み、手足の痛みやしびれ、足がもつれる等の症状が引き起こされます。これらの症状は、特に首を後ろに反らした時に強くなります。排尿・排便障害を伴うこともあります。
病院に行くべきタイミング
こりが軽度であり、生活習慣や姿勢に気をつける等の対策をして、日ごとに良くなっていくのであれば、過度に心配する必要がありません。
ただし、以下のような場合には、医療機関を受診すべきタイミングやケースと言えます。

- 首のこりとともに、寝違えた時のような痛み・鋭い痛みがある
- 首を動かすと痛みが強くなる
- 手足のしびれや痛み、脱力感がある
- 頭を強く打った後、首にこりや痛みが出た
もちろん、こりや痛みが軽いものでも受診していただけます。原因を早期に特定し、早期の治療・対策を行うのが理想です。
首のこりの診断と検査
問診・診察
首のこりについて、詳しくお伺いします。
また、視診・触診により、首周りの状態や動きを確認します。
レントゲン検査
頚椎の並びや椎間板の隙間、骨の変形やズレがないか、レントゲン検査を行います。
超音波検査
筋肉の炎症の有無や血流の状態、リンパの腫れなどを調べるため、超音波検査を行います。
MRI検査
レントゲンや超音波では見えない、神経・椎間板・筋肉・血管の状態をMRI検査で確認します。
その他CT検査、筋電図、神経伝導検査が必要な場合は連携病院等をご紹介します。
首のこりに行う治療
セルフケアと姿勢の見直し
意外に思われるかもしれませんが、ご自宅でのストレッチなどのセルフケア、普段の姿勢の見直しは、首のこりを治療する上で高い効果が期待できます。
ストレッチの方法、正しい姿勢については、医師・理学療法士から指導を行います。
※首に強い痛みがある場合には、自己流でのストレッチはお控えいただくのが無難です。
薬物療法
 痛み・炎症を抑えるための消炎鎮痛薬、解熱鎮痛薬、湿布などを処方します。
痛み・炎症を抑えるための消炎鎮痛薬、解熱鎮痛薬、湿布などを処方します。
また、関節・椎間板の圧力を弱めることを目的として、筋弛緩薬を使用することもあります。
基本的に対症療法となりますので、お薬だけに頼っていると、使用を終えた後の再発リスクが高まります。セルフケアと姿勢の見直し、リハビリテーションなどにも、しっかりと取り組んでいきましょう。
リハビリテーション
痛みが強い間は安静にしてください。首のサポーターを装着することもあります。
痛みが落ち着いてからは、温熱・電気・牽引などの物理療法を行います。
頚椎症・頚椎椎間板ヘルニアともに、牽引は有効です。
注射療法
(ハイドロリリース)
 薬物療法やリハビリテーションで十分な効果が得られない場合には、関節注射、トリガーポイント注射、ハイドロリリースなどを行います。
薬物療法やリハビリテーションで十分な効果が得られない場合には、関節注射、トリガーポイント注射、ハイドロリリースなどを行います。
日常生活でできる予防と
セルフケア
あらゆる姿勢の見直し
 座る時の姿勢、デスクワークをする時の姿勢、スマホを持つ時の姿勢、立つ・歩く時の姿勢、寝る時の姿勢など、さまざまな場面における姿勢を見直しましょう。
座る時の姿勢、デスクワークをする時の姿勢、スマホを持つ時の姿勢、立つ・歩く時の姿勢、寝る時の姿勢など、さまざまな場面における姿勢を見直しましょう。
前屈みになる・反る姿勢は首や肩・背中・腰などに負担をかけます。日中の姿勢については、頭を1本の細い糸で真上に引っ張られるような感覚で背筋を伸ばすと、首への負担が軽くなります。
デスクワークの方などは、正しい姿勢を維持しやすいよう、椅子の見直しが必要になることもあります。
体に合った枕の使用
 枕がなかなか決まらないという方も多いかと思います。
枕がなかなか決まらないという方も多いかと思います。
仰向けに寝た時、首の角度は自然に立っている(正しい姿勢で立っている)時と同じくらいになるのが理想的です。布団とのあいだに隙間ができますが、そこをきれいに埋められる枕を選びましょう。
とはいえ、後頭部の出方などによって適切な枕の高さは異なります。頻繁に買い替えるのも大変ですから、ぴったりのものが見つからない場合には、タオルなどで調整する方法がおすすめです。
生活習慣の改善
 規則正しい生活リズム、十分な睡眠、ストレスの解消、適度な運動により、生活習慣を改善しましょう。自律神経のバランスが整うこと、血流の改善や筋肉のリラックス効果が得られることなどから、首や肩のこりの予防に役立ちます。
規則正しい生活リズム、十分な睡眠、ストレスの解消、適度な運動により、生活習慣を改善しましょう。自律神経のバランスが整うこと、血流の改善や筋肉のリラックス効果が得られることなどから、首や肩のこりの予防に役立ちます。
ストレッチ
首のこりに有効とされるストレッチをご紹介します。
デスクワークの合間などにお試しください。
- 背筋をまっすぐにして立った状態で、腕を前方に伸ばして「前にならえ」をします。
- 手のひらを上に向け、肘を身体より後方までまっすぐ引きます。この時、左右の肩甲骨が近づくのを意識してください。
- その姿勢で、おへその下、お尻の穴にぎゅっと力を入れます。
- 力を抜き、姿勢を維持しながら、深呼吸をします。